葬儀から帰宅して玄関の前に立ったとき、ふとポケットの中の小袋に気づく。「あ、塩を使うの忘れた」——そのまま家に入ってしまい、後からじわじわと不安が込み上げてきた経験はありませんか?
清め塩の習慣は神道と仏教の死生観が混在した日本独特の慣習であり、「使うべきか」「身内も必要か」の正解は宗派や立場によって正反対になるのが実情です。本記事では、各宗派の公式見解や民俗学的な背景まで踏み込み、塩をまく理由・正しい手順・忘れた場合の対処法・身内の扱い・宗派ごとの考え方を網羅的に解説しています。
読み終えれば、次に葬儀に参列したとき「自分はどうすればいいか」を迷わず判断できるようになります。結論を先にお伝えすると、清め塩をしなくても罰が当たることはありません。大切なのは形式ではなく、故人への敬意です。
葬式後に塩をまく理由|清め塩の由来と意味

葬儀や通夜から帰宅した際に玄関先で塩を体にまく習慣は、主に神道の死生観に基づいています。
神道の「穢れを祓う」考え方と古事記の由来

神道では、「死」は「穢れ(けがれ)」であると考えられています。ただし、これは故人そのものが汚れているという意味ではありません。「穢れ」は「気枯れ(けがれ)」とも表記され、身近な人の死によって生命力が枯渇し、気力が衰えた状態を指します。この気枯れた状態には邪気が寄り付きやすいとされ、穢れを自宅に持ち込まないために塩で身を清める儀式が生まれました。
塩で清める考え方の起源は古く、日本最古の歴史書**『古事記』にも見られます。黄泉の国(死者の世界)から戻ったイザナギノミコト**が、海水で体を洗い清めて穢れを祓ったという記述が根拠です。
また、塩には古くから以下の力があると信じられてきました。
🔹 塩の浄化イメージ:
- 腐敗を防ぐ力(食料保存で経験的に知られていた)
- 物を清める力(殺菌・消毒の効果)
- 邪気を祓う力(神道の祭祀で使用されてきた歴史)
この塩が持つ浄化のイメージが神道の穢れを祓う考えと結びつき、「清め塩」の習慣が定着したと考えられています。神道の葬儀については「神道の葬儀費用はいくら?神葬祭の相場・内訳・仏式との違い」でも詳しく解説しています。
仏教では死を穢れと捉えない

一方で、仏教では死を穢れとは捉えません。仏教の死生観では、死は成仏や輪廻転生の過程であり、不浄なものではないとされています。そのため仏式の葬儀において、本来は清め塩の儀式は必要ありません。
| 宗派 | 清め塩への考え方 | 理由 |
|---|---|---|
| 浄土真宗 | 明確に反対 | 往生即成仏の教え。死を穢れとすることは故人への非礼 |
| 曹洞宗 | 公式に反対 | 教義上の理由に加え、死の穢れ思想が差別を助長するとの人権的配慮 |
| 臨済宗 | 統一見解なし | 地域慣習に従うことが多い |
| 真言宗 | 特別な規定なし | 地域慣習に従うことが多い |
それでも仏式の葬儀で清め塩が配られることがあるのは、神道の考え方が日本の生活慣習として深く根付いているためです。近年は仏教の教えに配慮し、清め塩を配布しない葬儀社も増えています。
清め塩の正しい使い方|手順・場所・タイミング
清め塩を使う場合の正しい手順を解説します。
使うタイミングと場所|玄関に入る前が基本

清め塩を使う最も一般的なタイミングは、通夜や葬儀・告別式から帰宅した際です。自宅に穢れを持ち込まないように、玄関に入る前に行うのが基本です。
| 住居タイプ | 清める場所 |
|---|---|
| 一軒家 | 門や玄関ドアの前 |
| マンション・アパート | 自室の玄関ドア前(共用廊下) |
| 実家暮らし | 建物に入る前 |
葬儀後に直帰しない場合(会社など別の場所に寄る場合)は、葬儀会場を出た際に足元に塩をまく方法もあります。スーツや服に塩が残る心配がなく、外出先に穢れを持ち込まないという考え方です。
まき方の手順|胸→背中→足元の順に払い落とす

正式な手順では、塩を使う前に手を水で洗い清めるとされています。ただし、玄関先で手を洗うのが難しい場合は省略しても問題ありません。家族が在宅であれば、水を持ってきてもらうとよいでしょう。
塩をまく手順は以下の通りです。
📋 基本的な手順:
- 塩をひとつまみ取る:清め塩を少量、指でつまむ
- 胸元に振りかける:心臓のあたりに塩をかける
- 背中に振りかける:肩越しに背中へ塩をかける
- 足元に振りかける:足元に塩をまく
- 塩を払い落とす:体にかけた塩を手でしっかり払う
- 足元の塩を踏む:地面に落ちた塩を踏んでから家に入る
「胸→背中→足元」という順番は、上から下へ穢れを払い落とすという伝統的な祓いの作法に基づいています。なお、一部のマナーサイトで「血流に沿った順番」とする説明が見られますが、これは民俗学的な根拠がない俗説です。実際には、身体の上部から下部へと穢れを地面に向かって落とすという物理的な浄化動作が本来の意味です。
また、背中に塩をかける理由には、日本の民俗信仰で「背中は霊や邪気が憑きやすい場所」とされてきた背景があります。完璧にできなくても、清める意識を持つことが大切です。

火葬場から戻った際の清め方

火葬場から葬儀場に戻る際にも清めを行う場合があります。帰宅時の手順とは異なり、以下の流れが一般的です。
📋 火葬場からの清めの手順:
- 両手のひらに塩をかけて清める
- 桶の水を柄杓ですくい、手を洗い流す
- 清め終えてから葬儀場に入る
宗派や地域によって方法が異なるため、葬儀場のスタッフの案内に従うのが確実です。浄土真宗の葬儀では塩ではなくおしぼりが配布される場合もあります。
自分でまく場合と家族に頼む場合
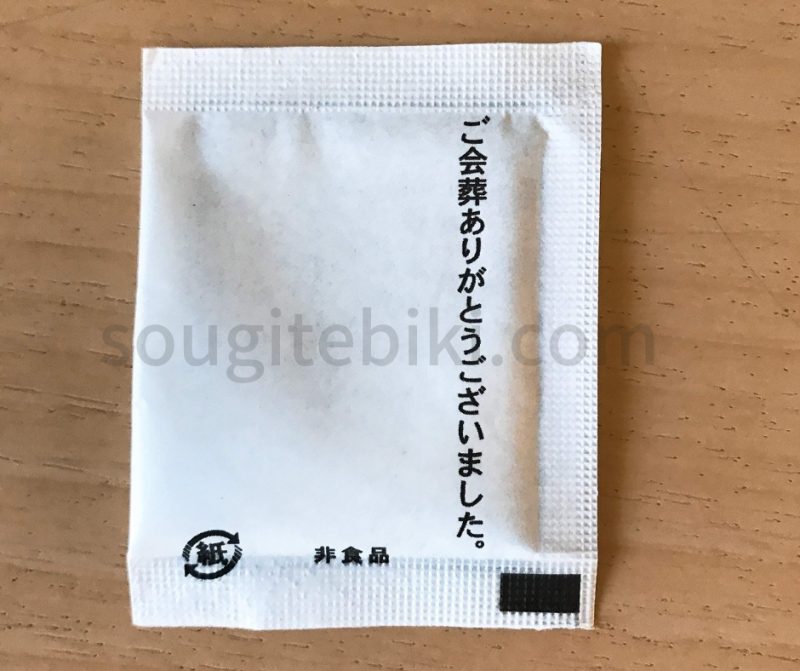
最も丁寧な方法は、葬儀に参列しなかった家族に玄関先で塩をかけてもらうことです。
以下のような場合は自分で行っても問題ありません。
🔹 自分で清める場合:
- 一人暮らしの場合
- 家族全員で葬儀に参列した場合
- 家族に頼むのが難しい場合
自分で行う際も、胸元→肩越しに背中→足元の順を意識すれば十分です。
葬式後に清め塩を忘れた場合の対処法
葬儀から帰宅した際、「うっかり塩を使うのを忘れて家に入ってしまった」「そもそも清め塩をもらい忘れた」ということもあるかもしれません。そのような場合でも、慌てる必要はありません。
忘れても問題ない理由

まず前提として、清め塩は絶対に行わなければならない儀式ではありません。
清め塩を使う習慣は神道の考え方に基づいています。「死は穢れである」と捉えない仏教では本来不要であり、特に浄土真宗や曹洞宗では清め塩の使用を教義上明確に否定しています。「忘れたから罰が当たる」といった性質のものではありません。
また、通夜振る舞いや精進落としの食事やお酒にも清めの意味があるとされています。葬儀後に食事の席に参加していれば、それ自体が清めの行為にあたるという考え方もあります。お酒には古くから邪気を祓う力があるとされており、焼香や参列のマナーと合わせて覚えておくと安心です。
後からやり直す方法と気持ちの整え方

とはいえ、「やはり清めないと気持ちが悪い」と感じる方もいるでしょう。その場合は以下の方法で対応できます。
一度玄関の外に出て、改めて塩で清めてから入り直せば問題ありません。「もう遅い」ということはなく、気持ちが落ち着くまで何度でもやり直せます。
清め塩の本質は形式そのものではなく、故人を敬い、自分自身の気持ちを整えることにあります。儀式の形にとらわれるよりも、ご自身が納得できるかどうかを判断基準にしましょう。
塩がない場合の代用方法|食塩・水での清め

手元に清め塩がない場合でも、以下の方法で代用できます。
🔹 代用方法:
- 家にある食塩を使う:海水100%の自然塩が望ましいとされるが、一般的な食卓塩でも問題ない。帰宅途中にコンビニで購入する方法もある
- 水で手や顔を洗い清める:水にも浄化の力があるとされ、古くから行われている清めの方法
- 地域の食べ物による清め:兵庫県・福井県では生米を食べる、味噌や豆腐を食べるなど地域独自の清め方法も存在する
清め塩がなくても、「これで清められた」とご自身が感じられれば十分です。
お清めの塩をしないとどうなる?

「お清めの塩をしなかったら何か悪いことが起きるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。
宗教的にも「罰が当たる」根拠はない
結論として、清め塩をしなくても罰が当たったり、不幸が起きたりすることはありません。
清め塩はあくまで神道の死生観に基づく慣習であり、宗教的な義務ではありません。仏教やキリスト教では死を穢れとは考えないため、これらの宗教の葬儀に参列した場合は、そもそも塩で清める必要がないとされています。
実際に、浄土真宗の門徒が多い広島県や新潟県では、清め塩を使わないことが一般的であり、それによって何か問題が起きているわけではありません。
気になる場合は後からでも対応できる
気持ちの面でどうしても不安が残る場合は、前述の「忘れた場合の対処法」で紹介した方法でいつでも後から対応できます。玄関の外に出てやり直す、食塩で代用する、水で清めるなど、方法は複数あります。
身内(遺族・親族)は清め塩を使わない理由

「身内は塩を使うのか?」という疑問について、故人の身内(遺族・親族)は基本的に使う必要がないとされています。
遺族が使わないとされる2つの理由
❶ 穢れとの関係性による理由
清め塩はもともと、外から持ち帰った穢れを家に入れる前に祓うためのものです。故人に最も近い存在である遺族・親族は、すでに穢れの中にいると考えられるため、清めの対象ではないとされます。
❷ 葬儀の主催者としての立場
遺族・親族は葬儀の主催者側であり、参列者をもてなす立場にあります。清め塩は弔問に来てくださった方が使うものであり、主催者側である身内が使うものではないという考え方です。
迷った場合の判断基準

清め塩を使うかどうかは、宗派の教え・地域の慣習・個人の気持ちのバランスで判断が分かれます。
「清めないと気持ちが落ち着かない」と感じるなら、形式的に塩を使っても間違いではありません。逆に、浄土真宗のように死を穢れと捉えない宗派に属している場合は、その教えを尊重することも大切です。
最も重要なのは、故人を悼み、敬う気持ちです。形式にとらわれすぎず、ご自身の信条に従って判断しましょう。
宗派別の清め塩に対する考え方

清め塩は神道の「死=穢れ」という考えに基づく習慣であるため、宗教や宗派によって対応が大きく異なります。
浄土真宗|教義上明確に使わない立場
浄土真宗では清め塩の使用を教義上明確に否定しています。
浄土真宗の教えでは、**「人は亡くなるとすぐに阿弥陀如来のおられる極楽浄土へ往き、仏になる(往生即成仏)」**とされています。死を「穢れ」や「不浄」として扱うことは、亡くなった故人を侮辱する行為とみなされます。
真宗大谷派(東本願寺)真宗会館の公式見解でも、清め塩について「仏教では決して死を穢れと受け止めない」「迷信や奇習を明確に否定していきたい」と明言しています。本願寺派・大谷派ともに同じ立場です。
浄土真宗の葬儀では、返礼品に清め塩を入れず、代わりに説明書きを同封したり、おしぼりを配布したりする対応が一般的になっています。
曹洞宗|公式に否定する教義的・人権的理由
曹洞宗も清め塩を公式に否定しています。その根拠は曹洞宗宗務庁が発行する啓発冊子**『曹洞宗ブックレット 宗教と人権4』**に明文化されており、曹洞宗の人権擁護推進活動の一環として位置づけられています。
曹洞宗の否定の理由は、教義面だけではありません。歴史的に「死=穢れ」という思想は、死や葬送に関わる人々への社会的差別を助長してきた側面があります。曹洞宗は、清め塩を使うことが**「死者を穢れたものとして扱う」差別的な思想を温存することにつながる**として、人権的な観点からも否定しています。
曹洞宗龍泰院の解説では、「仏教そのものが清めの塩など使わない」と述べたうえで、この見解が教団全体の方針に基づくものであることが説明されています。
その他の宗派・宗教の立場
| 宗派・宗教 | 清め塩への考え方 |
|---|---|
| 臨済宗 | 宗派として統一した見解はなく、地域の慣習に従うことが多い |
| 真言宗 | 特別な規定はなく、地域の慣習に従うことが多い |
| キリスト教 | 死を穢れとは考えず、清め塩を使う習慣は一切ない |
| 無宗教 | 宗教的な決まりがないため、喪主や遺族の判断に委ねられる |

まとめ

清め塩は神道の「死=穢れ」という考えに基づく慣習であり、塩で穢れを祓うために使われます。仏教では死を穢れと捉えないため、浄土真宗や曹洞宗では教義上明確に否定しています。キリスト教でも使用しません。
使用する場合の手順は、玄関に入る前に胸→背中→足元の順に塩をかけ、払い落としてから足元の塩を踏んで入ります。忘れても問題はなく、後からやり直すことも、食卓塩で代用することもできます。通夜振る舞いの食事も清めの意味を持つとされています。
身内(遺族・親族)は基本的に使用しません。ただし、使ってはいけないわけではなく、不安な場合は使っても構いません。最も大切なのは故人への敬意と感謝の気持ちです。形式にとらわれすぎず、ご自身の信条や地域の慣習を尊重しながら判断してください。
葬儀後の過ごし方については「忌中の違いと期間」も参考にしてください。
よくある質問|清め塩のQ&A
- 清め塩はどこで手に入る?
-
葬儀会場で会葬御礼(返礼品)と一緒に配布されるのが一般的です。会場の出口付近に用意されている場合もあります。手元にない場合は、家にある食塩で代用できます。
- 家の食塩で代用できる?
-
代用できます。海水100%の自然塩(粗塩)が望ましいとされますが、一般的な食卓塩でも問題ありません。
- 葬儀社の清め塩が「食用ではない」のはなぜ?
-
葬儀社が配布する清め塩は、食品衛生法上の「食品」としてではなく「雑貨」として製造されているためです。食品としての衛生管理基準(HACCPなど)を満たしておらず、工業用グレードの塩が使われている場合もあります。また、万が一の誤食を防ぐためのPL法(製造物責任法)上の警告表示でもあります。絶対に口にしないよう注意してください。
- 余った清め塩の処分方法は?
-
通常のゴミとして処分して問題ありません。特別な処分方法は必要なく、「バチが当たる」こともありません。気になる場合は庭にまいたり、水に流したりする方法もあります。
- 清め塩と盛り塩の違いは?
-
由来と目的が異なります。清め塩は神道の「穢れを祓う」考えに基づき、葬儀後に体にまく一回限りのものです。盛り塩は中国の故事に由来し、玄関や店先に三角錐状に置いて邪気を払い運気を呼ぶ、日常的な縁起担ぎです。
- お清めの塩はいつまでに使えばいい?
-
明確な期限はありません。基本は帰宅時に玄関前で使いますが、忘れた場合でも後から使えます。時間が経ったから効果がなくなるという性質のものではなく、気持ちの整理として行うものです。
【参考情報】









